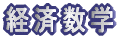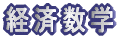差は、加減の根源であり、比は積と商の根源である。差と比から四則の演算は生じ、差と比は、演算の性格を決める。
数というのは、数えるとか、比較するという操作によって形成される。即ち、数は、操作的な概念である。数は、比較するにせよ、何と比較するか、又、数えるにせよ何によって数えるかが、重要となる。即ち、何を基準とするかである。基準とは単位である。
その上で、なぜ、比較するのか。何を数えるのかによって比を求めるか、数、即ち、差を求めるかを決めるのである。
比とは、要因であり、差は結果である。
現象は、一つの全体と変化する部分、そして、変化させる力からなる。全体は、位置として表され、変化する部分は、差として表される。変化させる力は、関係となる。そして、全体と変化する部分は、比として表すことが可能で、差は運動に置き換えることができる。
この比と差から、現象の背後にある関係、即ち、力の性質を解明するのである。
差は、幅として現れる。比は、率として表される。
何を重視すべきか。幅を重視すべきか、率を重視すべきか。それが重大となる。
経済が成長し、市場が拡大している時は、率、即ち、比が重視される。経済が停滞、ある意志は、縮小している時は、幅、即ち、差が問題となる。
比が問題となるのは、微分型の経済だからである。差が問題になるのは、積分型の経済だからである。微分型の経済とは、変化を分母としている経済であり、積分型の経済は、総量を分母とした経済なのである。
即ち、成長期から成熟期への経済の移行は、微分型の経済から積分型の経済への質的な転化があるのである。
成長期においては変化に基礎を置くべきだが成熟期では、全体の量に基礎を置くべきなのである。変化は運動であり、全体の量は位置である。即ち、運動から位置、動から静への転換が必要なのである。そして、動と静を仕切るのは関係である。位置と運動と関係から現象は解明される。位置と運動と関係を関数で表したのが、科学である。
数の本質は、比である。故に、数は相対的なのである。
定規によって定められた一定の長さを位置とする。その長さをコンパスに写し取って直線上に回転させることによって二が生じる。
一が定まることで、二が生まれる。二が成立することによって三が確定する。一となる値が単位となる。
数は、抽象であり、数字は象徴である。
比率には、全体に占める割合という意味と、変化の度合いという意味がある。税率や所得再分配などを考える上で、所得を全体に占める割合としてみるか、それとも前年と比較した伸び率として捉えるかによって経済に対する見方の質に違いがでる。特に、成長期においては、伸び率という見方が支配的になりやすいが、成熟期にはいると分配率という考え方に転換する必要がでてくる。
現代日本人は、数学の基礎を代数的な物に求める傾向がある。しかし近代数学の源であるギリシアでは、数は、比を基にして考えられた。
つまり、目盛りのない定規とコンパスによって数学の基礎は作られたのである。定規は、一定の長さを確定し、コンパスは、その長さを他に写像するために主として用いられた。つまり、普遍的に確定された量を単位としたのではなく。その時その時に決められて長さを単位としたのである。ギリシアにおいて普遍的な尺度として前提されたのは、特定の量ではなく、数である。そして、数は、量を比較するときに生じる率によって求められた。
つまり、ギリシア数学の基礎は幾何学なのである。代数と幾何が融合したのは近代である。この事は、数学を考える上で重大な前提である。
数学的な概念、即ち、科学や経済、会計において、比が重要な働きをしている。この幾何学的な働きを理解しなければ数学的現象は理解できない。
日本人にとってコンパスは、円を書くため道具に過ぎないが、ギリシア人にとってコンパスは、線分を切り取るための道具なのである。
変化は、差である。差の認識が、変化の認識である。差は距離である。位置の移動である。位置は、空間的距離のような目に見える位置と温度の違いのような目に見えない位置とがある。ここで言う位置とは目に見えない位置の変化も含む。
変化は、時間の関数でもある。
即ち、変化に対する認識は、差を元とする。差をどの様に認識し、捉えるかによって変化に対する考え方が定まる。変化に対する認識が数を生み出す。即ち、差は、数の前提である。
変化は差によって求められる。差は変化する以前の位置と変化後の位置によって求められる。差の値が明らかになれば、変化した部分と変化する以前の位置と比較することが可能となる。変化しない部分を固定的な部分、静止した部分とする。
数には、基数と序数がある。基数は、量を意味し、序数は、位置に基づく。
運動は、時間的な変化である。変化は、差によって認識される。差とは、位置の移動である。
経済的変化は、先ず、差から求められる。差は変化する以前の位置と変化後の位置によって求められる。
変化は差として認識されるが、変化の動きは、比を基本にする。
貨幣は、量的な単位ではなく、操作的な単位である。
貨幣単位を決める操作とは、比較と交換である。即ち、市場取引である。貨幣価値は、市場取引において出現する。
市場取引によって出現する貨幣価値は価格を形成する。価格は、取引と一対一の関係を有する。
差は、加減によって計算され、比は、乗除によって計算される。故に、差は同質な量を対象とし、比は、異質な量を生み出す。差は量の変化を表し、比は、質の変化を表す。
差も比も元(もと)となる数字が前提となる。元(もと)は、素(もと)である。
差は、分離量を素(もと)とし、比は連続量を素(もと)とする。差は、余剰を生みだし、比は割合を明らかにする。割合は、構成の素である。
構成とは、位置関係である。故に、構成は、比として現れる。対象を構成する要素は対象の性格の要因となる。対象の性格の要因は、対処の働きの素となる。即ち、対象の構成に従って差、即ち、変化が生じ、構成は、変化の原因となる。比は、変化の原因となり、変化の結果は、差によって認識される。
この様に、差と比とは、密接な関係がある。即ち、差は前提となり、比は、距離を測る。差と比とは、補完的関係にある。
変化は、差として認識されるが、構成は比によって認識される。
損益は、差として表されるが、残高、即ち、貸借は比として表される。
数は、相対的な概念である。故に、何を基とし、何を基準とし、何を単位とするかが重要となる。
経済で重要なのは変化をどう認識するかである。
変化には、比に基づく変化と差に基づく変化がある。比に基づく変化は率が重視され、差に基づく変化は幅が重要になる。
例えば、変動費は、率が問題となり、固定費は、幅が重要となる。変動費は速度の問題であり、固定費は量の問題である。速度は微分であり、量は積分である。
又、変化は、時間の関数である。変化の傾向を理解するためには、位置の移動を時系列で分析する必要がある。
変化を見極めるためには、全体の変化と部分の変化、構成の変化を見る必要がある。
ある全体を幾つかの部分に分割する事によって数は成り立っている。引くのか、割るのか、分割の仕方によって差となるか、比となるかが決まる。
全体の変化を数列として捉え、部分の変化も数列とし、構成の変化も数列にする。それによって現在の状況を過去から捉え、現在の状況から将来を予測する。それが経済数学の役割の一つである。
時系列的に経済的価値を考える上では、現在価値の算出が重要になる。
分析とは、全体を引いたり、割ったりして分かつことから始まるのである。そして、最初の全体とは何か。引いたり、割ったりする基準は何にするか、それは結果に対して重大な前提条件となる。
基準となる位置や値をどう設定するかによって結果の方向性が決まる。それは分析の目的によるのである。
差は、同質の量の間で行われる演算の結果である。
差にはいろいろある。例えば、身長の差、利益の差、収益の差、資本の規模の差、時間的な差である。しかし、いずれにしても差は、同質の量の減算の結果である。そこに差の持つ意義がある。加減は、同質の量の演算である。
それに対し、乗除は、量の質、即ち、次元をかえる演算である。
例えば、電気量から自動車の台数、ステーキの味、質は引けないし、足せないし、掛けられないし、割れないのである。電気と自動車が引いたり、足したり、掛けたり、割れるのは、電気料と自動車、ステーキの価格である。即ち、電気、自動車が貨幣価値に還元されることによってである。
電気や自動車、ステーキの価値を貨幣価値、即ち、価格に変換するために操作、演算が電気や自動車、ステーキの量に単価を掛け合わせることである。単価とは、財の単位あたりの貨幣価値である。
我々は、貨幣価値に換算することによって財の差を統一的に算出することが可能となるのである。
そして、経済において重要なのは、時間と空間によって生じる差である。なぜならば、経済的な価値は差によって生じるからである。故に、変化が識別、判別できるようになることが重要となる。
数式の重要な要素に視覚性と操作性の二点がある。視覚性というと、変化を数列として表現できれば、後は図形化することは簡単である。数列は、変化を視覚化するのである。
時間的変化は、数列として表される。時間的変化を推移という。経済で決定的な働きをするのは、時間と空間の距離、即ち、差である。そして、その時間と空間の距離に関わる力である。
時間的に差を生み出す要因は時間価値である。
時間価値には、金利、利益、配当、物価上昇率、所得の上昇率、地価の上昇率などがある。
気温の変化、人口の変化、作物の生産高の変化、これらは数列として表現することが可能である。変化の性質や傾向は、数列を分析することによって明らかにすることができる。
時系列的に考えると長期的な変動と短期的な変動がある。会計的に言うと、単位期間内に現れる変動と単位期間内には現れない変動があると想定される。そして、単位期間内に現れる変動を流動性というのである。
統計資料が充実してきた今日、経済状況や企業実績は、数列として表すことが可能となってきた。
何を以て企業の実態を評価するのか。又、何を根拠に融資や投資を行うのか。それが問題なのである。
経済的変動の根本は差である。つまり、経済的変動、経済的な差が生じる原因が重要なのである。しかし、問題なのは、その根拠となるデータ、数値である。経済的価値の根拠が創られた概念に基づいて導き出された値だとしたら、差が生じる根拠が重要となる。
我々は、利益を収益と費用の差だと単純に教わる。しかし、収益とは、何か、費用とは何かと言う事に対する明確な定義は教えられない。収益や費用が会計的につくられた数字であるという事も教えられない。教えられたとしても、収益や費用がどの様にして定義され、定められたかについては謎のままである。それでは、利益は、何かの差だと言う事以外、明らかにされていないのと同じである。
利益は、収支と違い、現金、即ち、実現した貨幣価値の裏付けがあるわけではないのである。利益は、任意に決められた特定の基準によって導き出された値を根拠にしているだけなのである。
それをあたかも自然の法則の如く確定した真理のように扱うことは愚かである。
数列を設定する上で重要となるのは、基となる部分と変動する部分をどの様に設定するかである。又、座標軸をどの様に引くかである。
比率を設定する場合は、何を元(もと)とするかであり、元に対して比率は、外在的な比率か、内在的な比率かである。それによって比率の働きに差が生じる。
何に基づく比率かによって計算の結果や率の持つ意味に違いが生じる。
例えば、純額主義をとるか、総額主義をとるかによって率に違いが生じる。
外在的比率か、内在的比率かによって比率の持つ意味や働きに違いが出る。同じ税率でも消費税は外在的比率であり、所得税は内在的な比率である。
時系列的に差と比を比べると、経済成長は、率を基本にして現れる。経済変動は、複利的な現象なのである。
時間的価値の代表に金利がある。金利には単利と複利がある。
単利は、差に基づいた概念であり、複利は、比に基づいた概念である。故に、単利は、幅を重視し、複利は率を重視する。
利益は差である。収支も差である。利益は、単位期間内の収益と費用の差として表現される。収支は、収入と支出の差である。利益と現金収支は違う。
利益は比によって働きが明らかにされる。即ち、収益や費用との比や資産や負債、資本との比によって利益の持つ役割や意味が明らかになる。
収支は差によって実体を明らかにする。収支が、負の残高になれば、企業の継続は断たれる。ただ、収支だけでは、結果しか明らかにできない。故に、期間損益計算が必要とされるのである。
問題は、利益計算や収支計算が何に基づくかである。
気を付けなければならないのは、利益は会計的概念であり、抽象的な概念だと言う事である。
利益は、観念上の差である。実体的な差ではない。つまり、現金収入と現金支出の差ではない。また、財の入庫と出庫の差でもない。あくまでも、収入、費用という抽象概念の差である。つまり、つくられた数字上の差である。故に、収入と費用をどの様に定義するかによって利益に差が生じる。
所得や消費も、期間損益に基づく、即ち、認識上に発生する概念である。現金の裏付けがあるわけではない。
所得税や消費税を課す場合は、実体経済に与える影響、特に、資金の流れに与える影響を充分に考慮しておく必要がある。
経済変動や企業実績は、数列として表すことができる。ただし、経済変動や企業実績を表す数値の変化は、その背後にある方程式や前提条件によって違ってくる。つまり、方程式を定式化し、前提条件を厳格に管理する必要があるのである。そして、それが会計という制度を生み出す下地となったのである。
故に、会計制度は、複数の命題を定義、基準として前提とする公理主義的な制度にならざるを得ない。即ち、会計制度は、高度に数学的な制度なのである。
会計制度を基盤とした近代経済体制は、きわめて数学的体制である。
数列が成り立つ為には、数列を成り立たせている世界があることを忘れてはならない。数列に意味を持たせる存在があるとしたら、それは、数列を成り立たせている世界の側にあることを忘れてはならない。数列ばかりを見ていたら、数列の持つ真の意味を理解することはできないのである。
会計の中には、フェボナッチの数列が隠れている。それが重要な意味がある。
収入の1、支出の1、貸借の2,資産、負債、資本の3、資産、負債、資本、収益、費用の5,資産、負債、資本、収益、費用、営業キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、投資キャッシュフローの8。これは一例である。
比とは、要因であり、差は結果である。
現象を構成する要素は、一つの全体と変化する部分、そして、変化させる力である。全体は、一つの基準単位とすることができる。部分も一つの単位とすることができる。
全体は、位置として表され、変化する部分は、差として表される。
変化させる力は、変化する部分に対する働きである。
比は、全体と部分によって成立し、差は力によって決まる。力は方向と量から構成される。
全体と変化する部分は、比として表すことができる。差を時間的に並べ連続させることによって変化の軌跡を割り出す事によって運動を導く出すことができる。
この比と差から、現象の背後にある関係、即ち、力の性質を解明するのである。
比にしろ、差にしろ、何を基準にするかにかかっている。比にするか、差にするかですら、基準を選択する動機、目的に依っているのである。
会計結果は、当初設定された前提を延長したところに成立する数値である。故に、初期設定、初期条件が重要となる。経済的価値の多くが同様なことが言える。つまり、会計は、歴史的産物である。
何を基準とするかは、何を全体とするかである。つまりは、何を一とするかである。一とは単位である。それによって、比が適切か、差が適切かが判定される。
収益とは何か。利益とは何かである。収益とは、一つの全体であり、利益とは、差である。
経営の目的として利益率をとるか、量をとるか、占有率をとるか、それが問題なのである。全ての最大化を計ろうとするのは欲張りである。重要なのは何を最適とするかである。
売上を基準とするか、粗利益を基準とするかで構成比は違ってくる。
企業や産業の規模、或いは、資金の回転率を知りたいと思えば売上は、重要な基準となる。それに対して、付加価値や費用の効率を分析する場合には、粗利益の方が効果的である。
産業や企業の性格を知るためには、固定費と変動費の構成比が重要になる。しかし、利益を比較する場合には、比率よりも差の方が有効である場合がある。前期が赤で今期が黒字などと言った場合、比率では比較のしようがない場合もある。
要するに、企業や産業の事態を知るためには、何を基準にとるかが、重要なのであり、何を基準にするかは、何を知りたいか、即ち、目的に依るのである。
現象を構成する要素は、位置と運動と関係である。位置とは、静止した部分で運動とは、可動する部分と言う事もできる。そして、静止した部分と可動する部分の比率、幅、中心、性質、原因が重要となる。
性質というのは、変化が一時的なものか、恒常的な変化か、周期的な変化と言ったことである。
性質を知る上には、変化の速度や期間も重要な要素となる。
この様な位置や運動や関係の働きを知るためには、何の目的で何を知りたいかが、鍵を握る。それによって何を基準としてどの様に比較するかが決まるのである。
差が善いか、比が善いかは、目的によって決まるのであり、一概に、決まることではない。重要なのは前提である。



このホームページはリンク・フリーです
ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures
belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout
permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2009.12.20 Keiichirou Koyano